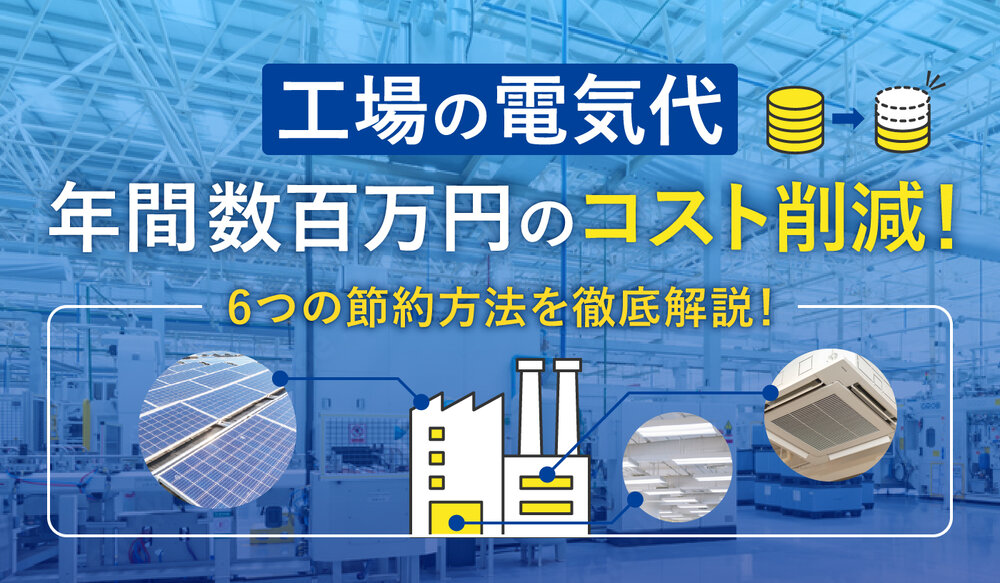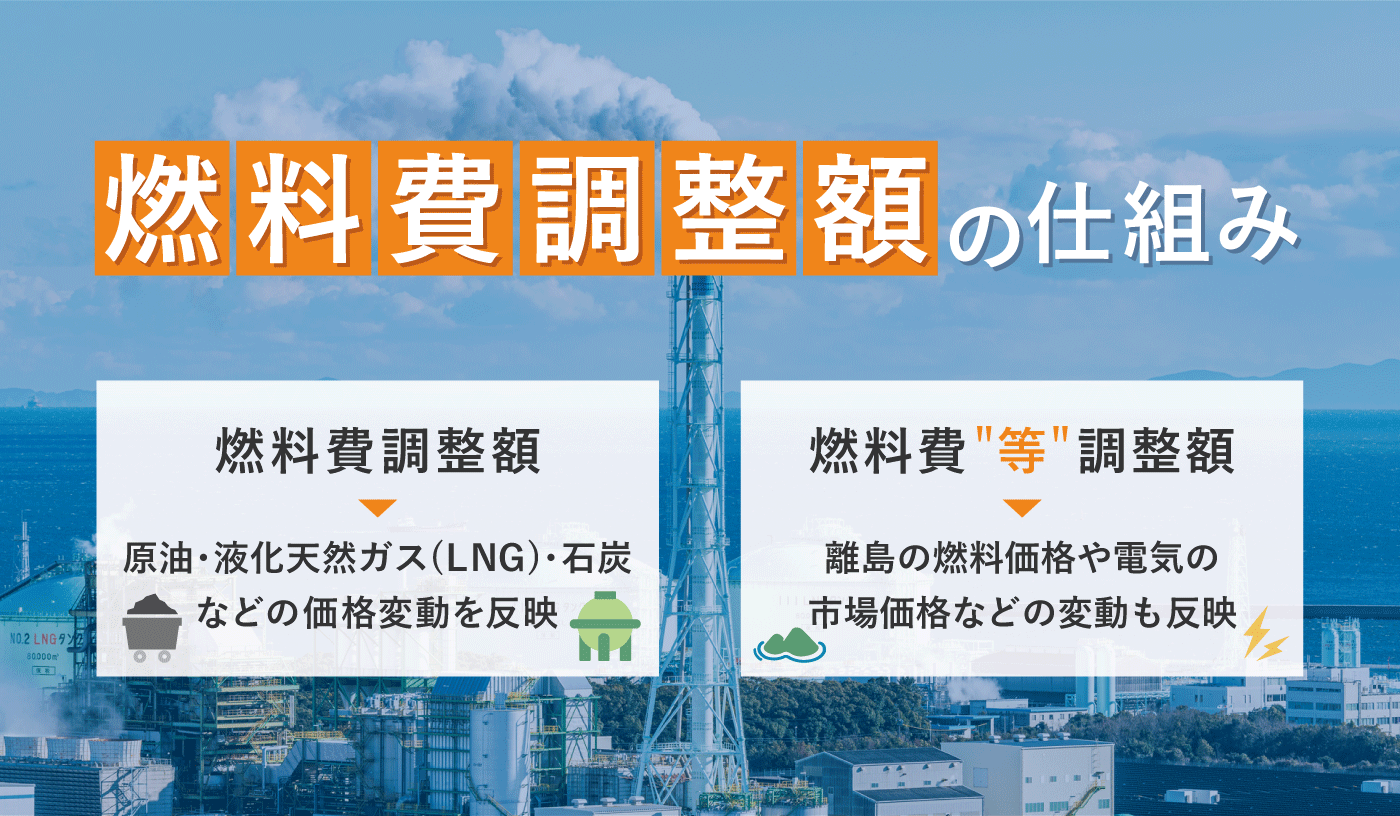バイオ燃料とは? 種類や原料、製造方法を徹底解説

バイオ燃料は、化石燃料の代替品として開発された次世代燃料です。再生可能エネルギーの一つで、燃料転換をすることで温室効果ガス(GHG)排出量を削減できます。
脱炭素経営に向けて事業活動にバイオ燃料を取り入れたいものの、種類が多く、それぞれの違いもよく分からないとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで本記事では、バイオ燃料の種類やそれぞれの原料・製造方法などについて詳しく解説します。
目次
バイオ燃料とは?
バイオ燃料は、石油や石炭、天然ガスといった有限な化石燃料とは異なり、食品廃棄物や農業廃棄物、家畜の排泄物、廃材などから作られる再生可能エネルギーの一つです。一般的には廃棄されるものを原料に、さまざまなプロセスを経て燃料となり、単独で利用するものもあれば、ガソリンや軽油と混ぜて使うものもあります。
液体バイオ燃料の歴史は意外と古く、1900年のパリ万博で発表されたディーゼルエンジンには、バイオディーゼルが使われていました。またアメリカでは、1973年のオイルショックをきっかけに生産量が急増しました。
日本では、1997年に京都で開かれた「気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)」にてバイオ燃料の活用について言及されており、近年では、原油価格の高騰や脱炭素化への関心の高まりから、化石燃料に代わるエネルギーとして再注目されています。
合成燃料との違い
脱炭素化を目指す上で注目されている燃料の一つに、合成燃料もあります。バイオ燃料が植物や食品廃棄物などのバイオマス資源を原料とするのに対して、合成燃料は二酸化炭素(CO₂)と水素(H₂)を合成して作られます。合成燃料もバイオ燃料と同じく、再生可能エネルギーに分類されます。
ただし、工場や発電所から排出される二酸化炭素と水素を利用する場合、その水素が石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料から抽出されたものであれば、CO₂は排出されませんが、カーボンニュートラルの観点からは評価されません。
一方で、太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用して水を電気分解し、水素を生成して合成燃料を製造する方法もあります。この方法で製造された合成燃料は「e-fuel(イーフューエル)」と呼ばれ、より環境に優しい燃料として期待されており、現在、各企業が将来の実用化へ向けて研究・開発を進めています。
バイオ燃料の種類
バイオ燃料にはいくつかの種類があり、原料によって第1~3世代に分類することができます。本記事では、代表的なバイオ燃料を以下の4つに分けてご紹介します。
- 第1世代バイオ燃料:バイオエタノール・バイオディーゼル(FAME)
- 第2世代バイオ燃料:バイオエタノール・FAME・HVO
- 第3世代バイオ燃料
- その他のバイオ燃料:バイオジェット(SAF)・メタン(バイオガス)
※バイオジェットは基本的に第2世代ですが、便宜上、その他区分として記載しています
第1世代バイオ燃料
第1世代バイオ燃料には、トウモロコシやサトウキビなどの可食部を原料とするバイオエタノールや、植物油をメタノールと反応させる比較的簡単なプロセスで製造できるバイオディーゼル(FAME)があります。第1世代バイオ燃料はガソリンや軽油の代替燃料としてアメリカやブラジルを中心に普及しており、比較的低コストで生産可能です。生産国では、化石燃料と同等レベルの価格競争力を持ちます。
一方で、食料として利用できる作物を原料にするため、食糧不足や穀物価格の高騰を引き起こす可能性や、大規模な農地確保による環境破壊が指摘されています。またFAMEは、低温流動性や貯蔵安定性に課題があり、基本的には化石燃料との混合利用が前提となっています。
第2世代バイオ燃料
第2世代バイオ燃料は、非可食バイオマスを原料とする燃料で、大きく植物の非可食部を原料とするセルロース系燃料と、動植物油や廃食用油などを原料とする燃料の2つに分類されます。第1世代バイオ燃料とは異なり食料と競合しないというメリットがあり、現在、第1世代からの移行が進んでいます。
第2世代バイオ燃料には他にも、温室効果ガス(GHG)の排出削減効果が高いことや、化石燃料とそのまま置き換え可能な「ドロップイン燃料」であることといったメリットがありますが、一方で、水素化精製などの化学的処理が必要であることから、製造コストの高さが課題となっています。
セルロース系燃料は主にバイオエタノール(ガソリン代替燃料)として利用され、ガソリンにバイオエタノールを5%混合している場合は「E5」、10%混合している場合は「E10」のように表記されます。米国ではE10ガソリンが販売されており、各国でバイオエタノールへの車両対応が進められています。
動植物油や廃食用油などを原料とする燃料はさらに従来型バイオ燃料(FAME)と次世代型バイオ燃料(HVO)に分類され、主にバイオディーゼル(軽油代替)として利用されています。
FAME(Fatty Acid Methyl Ester:脂肪酸メチルエステル)
FAMEは動植物油や廃食用油を原料に、メチルエステル化処理をして製造される軽油代替燃料です。後述するHVOに比べて製造しやすく、安価なのが特長です。
一方で、低温流動性や貯蔵安定性といった性能が軽油に比べて劣っており、基本的には軽油との混合利用が前提となっています。
FAMEの詳細は以下の通りです。
| 主な使用用途 | ディーゼルエンジン用燃料、船舶用燃料 |
| 主な原料 | 植物性油(菜種油、パーム油、オリーブ油、ひまわり油、大豆油、米油、麻実油)、廃食用油(天ぷら油など)、動物性油(魚油や豚脂、牛脂) |
| 主な製造方法 | メチルエステル化処理 |
なお、FAMEは一般的には「B100」や「BDF」と呼ばれています。「B〇〇」の数字が表すのは軽油との混和率で、「B5」なら軽油に5%のBDF、「B30」なら軽油に30%のBDFを混和しています。B100は、BDF100%です。
HVO(Hydrotreated Vegetable Oil:水素化バイオ燃料)
HVOは動植物油や廃食用油などを原料に、水素化処理をして製造される軽油代替燃料です。パラフィン系炭化水素のため、従来の軽油と構造が同じで、軽油と混合せずに単体で使用することが可能です。また低温流動性に優れており寒冷地でも使えたり、芳香族化合物が含まれていないため軽油よりもクリーンに使えたりします。
課題は製造コストが比較的高いことです。
HVOの詳細は以下の通りです。
| 主な使用用途 | ディーゼルエンジン用燃料、船舶用燃料 |
| 主な原料 | 植物性油(菜種油、パーム油、オリーブ油、ひまわり油、大豆油、米油、麻実油)、廃食用油(天ぷら油など)、動物性油(魚油や豚脂、牛脂) |
| 主な製造方法 | 水素化処理(HEFA)、ATJ |
FAMEとRD(HVO)の違い
FAMEとRD(HVO)は、いずれも軽油代替燃料で、原料もほぼ同じです。異なる点は製造方法と化学式、各法令上の位置づけです。
| FAME | RD(HVO) | |
| 主な原料 | 植物性油(菜種油、パーム油、オリーブ油、ひまわり油、大豆油、米油、麻実油)、廃食用油(天ぷら油など)、動物性油(魚油や豚脂、牛脂) | 植物性油(菜種油、パーム油、オリーブ油、ひまわり油、大豆油、米油、麻実油)、廃食用油(天ぷら油など)、動物性油(魚油や豚脂、牛脂) |
| 主な製造方法 | メチルエステル化処理 | 水素化処理 |
以下でさらに詳しく解説します。
原料
FAMEとRDの原料は基本的に同じで、動植物油や廃食用油が主です。
製造方法
FAMEとRDの違いは、製造方法にあります。FAMEはメチルエステル化処理によって製造されるのに対し、RDは水素化処理によって製造されます。
化学式
処理後にFAMEはエステル、RDは炭化水素となります。石油由来の軽油は炭化水素なので、RDは軽油と100%置き換えることが可能です(品確法上)。
各法律における分類
軽油に関する法律にはさまざまなものがありますが、それぞれの法律によって、また軽油との混和率によって、FAMEやRDの取り扱いは異なります。
詳細は以下の通りです。ただし、以下の表は法令上の区分や一般的な理解です。実際には事業者により異なる運用・制限を設けている場合もあるため、詳細は各燃料取扱事業者にお問い合わせください。
| B100 | B30 | B5 | RD | RD40 | |
| 軽油との混和率 | 100%BDF | 軽油に30%BDFを混和 | 軽油に5%BDFを混和 | 100%RD | 軽油に40%RDを混和 |
| 軽油対比CO2削減率 | ▲100.0% | ▲30.0% | ▲5.0% | ▲100.0% | ▲40.0% |
| 品確法 | 軽油ではない | 軽油ではない | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 地方税法 | 軽油ではない | ※各県税に確認 | 軽油 | 軽油ではない | 軽油 |
| 軽油引取税 | 対象外 | ※各県税に確認 | 対象 | オンロードで使用の場合:課税対象 オフロードで使用の場合:課税対象外 | 対象 |
| 公道での使用 | ※オンロードで使用は、自己責任 | ※各県税に確認 | 可 | 可 ※オンロードで使用の場合は、「自動車用炭化水素油譲渡証」の携帯が必須 | 可 |
| 注意事項他 | 軽油との混和不可 | ※各県税に確認 | 軽油と同様に使用可能 | 軽油との混和不可 | 軽油と同様に使用可能 |
第3世代バイオ燃料
第3世代バイオ燃料は微細藻類を原料とした燃料です。単位面積当たりの生産効率が非常に高く、温室効果ガス(GHG)排出量削減効果は第2世代と同等以上とされているため、将来的な実用化への期待が高まっています。
しかし、2025年現在では第2世代と同様にコスト面での課題が大きく、一部の企業は事業化を断念しています。現時点では実用化に至っていませんが、引き続き研究・開発が進められています。
その他のバイオ燃料:バイオジェット(SAF)
バイオ燃料の代表的な種類に、ジェット代替燃料のSAFもあります。詳細は以下の通りです。
| 主な使用用途 | ジェット燃料 |
| 主な原料 | 廃食用油(天ぷら油など)、バイオエタノール、植物(ナンヨウアブラギリ、アマナズナ)、木材チップ、微細藻類(ミドリムシ、ミカヅキモ)、牛脂 |
| 主な製造方法 | 水素化処理(HEFA)、ATJ |
SAFは、航空機のジェット燃料の代替品として開発されました。SAFにはいくつかの製造方法がありますが、現時点で社会実装に至っているのは「HEFA」と「ATJ」という技術です。HEFAは、廃食用油や牛脂などの原料を水素化処理することによってSAFを製造します。一方、ATJは、触媒を用いてバイオエタノールを脱水し、それによって得られるエチレンを重合させることによってSAFを製造します。なお、SAFと同時にHVOも精製されます。
その他のバイオ燃料:メタン(バイオガス)
ここまで挙げたバイオ燃料は液体ですが、メタンは気体のバイオ燃料です。詳細は以下の通りです。
| 主な使用用途 | 発電用燃料・熱供給用燃料 |
| 主な原料 | 動物の排せつ物、生ごみ、生分解性物質、汚泥、汚水 |
| 主な製造方法 | 嫌気性発酵(メタン発酵) |
メタンは有機廃棄物をメタン発酵させることで製造します。食料と競合しない上、廃棄物を原料とするため無駄がありません。主に発電やボイラーなどのエネルギー源として利用されています。
伊藤忠エネクスのRD(リニューアブルディーゼル)
伊藤忠エネクスの供給している次世代バイオ燃料「RD(リニューアブルディーゼル)」は、トラックやバス、船、建設機器などの燃料として活用されています。
製造元はフィンランドのNESTE社で、再生可能な燃料や原料を扱う世界有数のエネルギー会社です。伊藤忠商事が輸入・調達し、伊藤忠エネクスが供給・販売する仕組みとなっています。伊藤忠エネクスはISCC(国際持続可能性カーボン認証)を取得しており、また2024年6月21日にはRDが合成燃料の類型として初のエコマーク商品に認定されており、高い信頼性を誇ります。
RDを取り入れて脱炭素経営を目指したい場合や、バイオ燃料を取り入れたいものの、疑問が多く先に進めないとお悩みの場合は、伊藤忠エネクスにお気軽にお問い合わせください。RDに関する詳細情報や導入方法、導入後の流れなどを詳しくご紹介します。
リニューアブルディーゼル
03-4233-8073 enex_hvo@itcenex.com導入事例
伊藤忠エネクスのRDの導入実績として、東京都の事例が挙げられます。
東京都では脱炭素化に加え、バイオ燃料関連産業の活性化への寄与を目的に「バイオ燃料活用における事業化促進支援事業」を実施しています。伊藤忠エネクスはオーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン株式会社、三愛オブリ株式会社、サントリーホールディングス株式会社、全日本空輸株式会社および日本コンテナ輸送株式会社の連合各社とともにこの事業に応募し、支援対象として選ばれました。各社の陸上輸送車両や空港施設の作業車両にRDを供給することで、東京都の脱炭素化に貢献しています。
他にも多種多様な業界で伊藤忠エネクスのRDの供給が進んでいます。詳しくは、プレスリリース一覧をご確認ください。
まとめ
バイオ燃料は、今後企業が事業活動をする上で重要な脱炭素経営に貢献できます。第2世代バイオ燃料の中でも、次世代バイオ燃料と呼ばれているRD(リニューアブルディーゼル)は、食料と競合しない廃食用油や廃動植物油といった10種類以上の廃棄する油を原料としています。また石油由来の軽油の100%代替品として活用できる品質の高さも特長です。
伊藤忠エネクスでは、多くの業界で利用されている実績のある、信頼性の高いRDを供給しています。RDを導入したいとお考えの方や詳しく知りたい方は、お気軽に伊藤忠エネクスへご相談ください。
リニューアブルディーゼル
03-4233-8073 enex_hvo@itcenex.com\社用車から排出されるCO₂削減にお困りの方はこちら/
一覧へ戻る 一覧へ戻るキーワード検索
キーワード検索