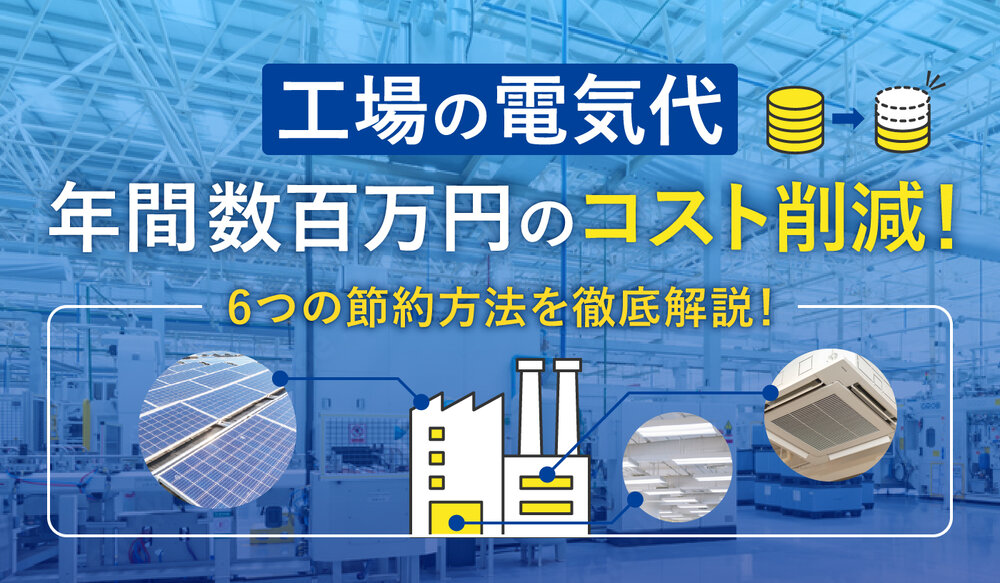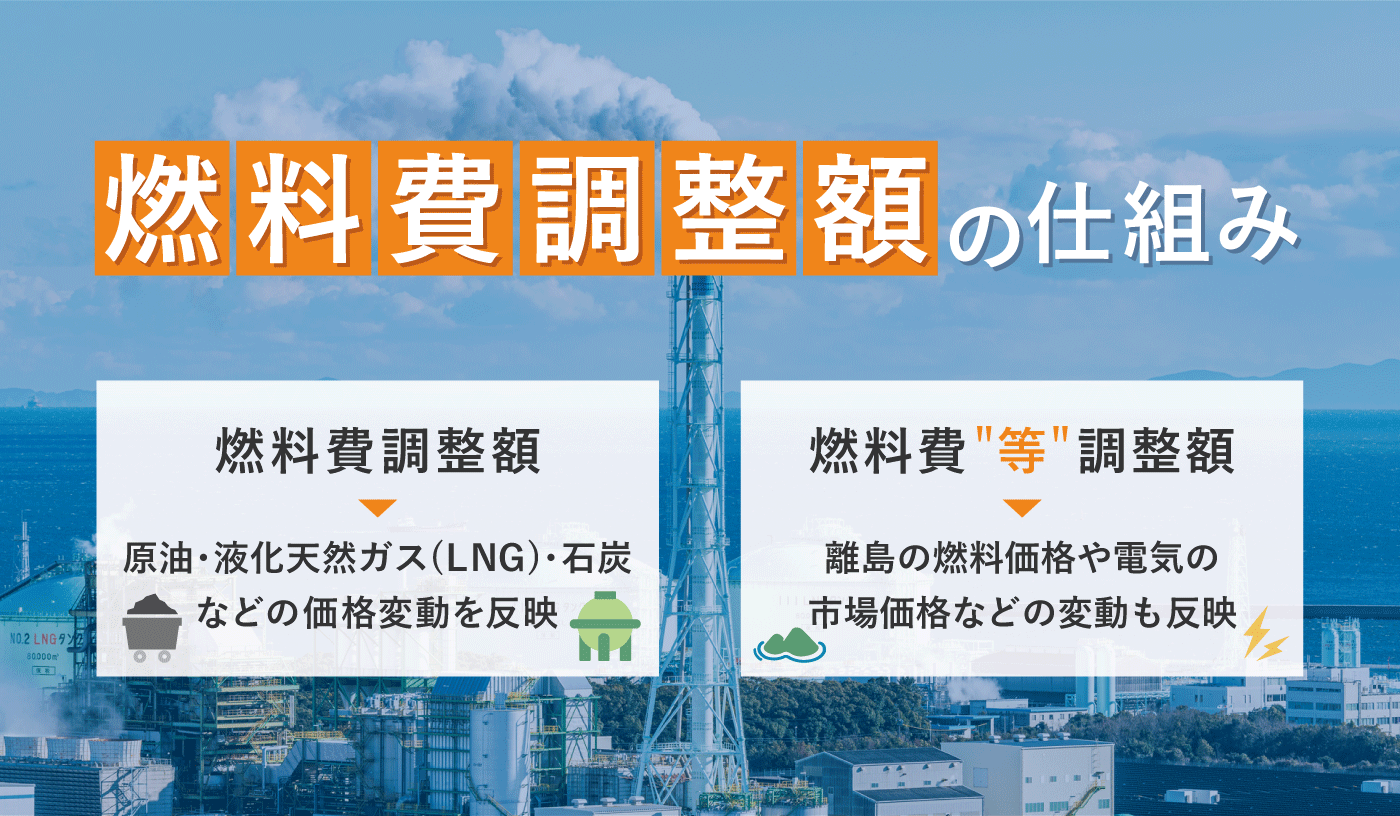自家消費型太陽光発電とは?メリットや注意点、導入事例などをご紹介!
太陽光発電のPPAモデルとは?仕組みや導入によるメリット・デメリットを解説!

環境問題への社会的な関心が高まる中、初期投資なしに太陽光発電システムを導入できる「PPAモデル」が注目されています。PPAモデルは、自社が保有する土地に第三者が太陽光発電設備を設置し、そこから生み出される電気を利用する、太陽光発電システムの導入方法の一つです。
本記事では、PPAモデルの仕組みやメリット・デメリットなど、PPAモデルの基礎知識について詳しく解説します。
※本記事は2024年12月時点の情報です
目次
PPAモデルとは?
PPAモデルとは「Power Purchase Agreement/電力販売契約」の略で、自家消費型太陽光発電の導入方法の1つであり、「第三者所有モデル」とも呼ばれます。PPA事業者が、需要家(電力を利用する企業や一般家庭)の保有する建物の屋根の上や、遊休地に太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を需要家がPPA事業者から買い取って使用する仕組みです。
通常、自己投資で太陽光発電システムを導入する際には多額の投資費用の準備が必要になります。しかし、PPAモデルでは初期投資不要で発電設備を導入できる上に、年次点検や故障時の保険の手配などはPPA事業者が行うため、手軽に太陽光発電システムを導入できる仕組みとして、昨今注目を集めています。
自家消費型太陽光発電については、以下の記事で詳しく解説しています。
PPAモデルの仕組み
PPAモデルでは、PPA事業者と需要家が「電力購入契約」を結び、PPA事業者が所有する太陽光発電設備を需要家が所有する建物の屋根の上や敷地内の遊休地に設置します。そして、その発電設備で発電された電気をPPA事業者が需要家へ供給し、需要家は使用した分の電気料金を毎月PPA事業者に支払います。
PPAモデル・自己所有型・リースの違い
太陽光発電システムを導入する方法としては、PPAモデルの他にも以下の2種類があります。
- 自己所有型
- リース
それぞれについて、解説します。
自己所有型
自己所有型は、太陽光発電システムの設備を自社で保有する方法です。自社の設備で発電した電気を自ら消費することで電気料金を削減できますが、PPAモデルとは異なり、設備の導入費用や設置後のメンテナンス費用などは自社で負担する必要があります。
FIT制度(固定価格買取制度)を活用して発電した電気を電力会社に売却し、売電収入を得ることも可能です。しかし、近年はFIT制度での買取価格が下落しており、以前ほどの収益を上げることが難しくなってきています。
リース
リースは、リース業者が所有する太陽光発電システムの設備を借りて使用する方法です。PPAモデルと同様に初期投資が不要で、メンテナンスもリース業者が行ってくれますが、導入期間中は毎月リース料を支払う必要があります。
一方で、自己所有型と同様、発電した電気は無料で使用でき、余剰電力で売電収入を得ることもできます。PPAモデルとは異なり、契約期間が終了すると設備はリース会社に返還しなければならない点がデメリットです。
| PPA | 自己所有 | リース | |
| 発電設備の所有者 | PPA事業者 | 需要家 | リース業者 |
| 初期投資 | 不要 | 必要 | 不要 |
| メンテナンス | 不要(PPA事業者) | 必要 | 不要(リース業者) |
| 利用料金 | 従量払い(太陽光電力使用量 × 固定単価) | 不要 | 必要(リース料) |
| 契約終了後の発電設備 | 残る | ― | 残らない |
PPAモデルの2つの種類
PPAモデルは、以下の2つに分類できます。
- オンサイトPPA
- オフサイトPPA
オンサイトPPA
オンサイトPPAでは、需要家の敷地内に太陽光発電設備を設置します。設置する場所としては自社の社屋や工場の屋上・屋根、カーポート、遊休地などが一般的です。発電した電気は、敷地内の設備で使用することができます。敷地内に設置するため、非常用電源としても活用可能です。
また発電した電力を自家消費のみで利用する場合、基本的には再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)がかかりません。さらに送配電網を使用しないため、託送料金もかからない点がメリットです。
最も一般的なPPAモデルはこのオンサイトPPAです。
オフサイトPPA
オフサイトPPAでは、需要家の敷地外に太陽光発電設備を設置します。耐荷重の問題から屋根の上に設備を設置できない場合や、敷地内に設備を設置するスペースがない場合、遊休地を所有していない場合などでも再エネ由来の電力を使用することができます。
オフサイトPPAは、小売電気事業者を介して電気を送電するため、自社の複数の事業所や工場に電力を供給できる点が特長です。一方で、小売電気事業者を介すため、オンサイトPPAとは異なり再エネ賦課金がかかります。
なお、オフサイトPPAは電力の受け取り方によって、さらに以下の2種類に分類できます。
- フィジカルPPA
- バーチャルPPA
フィジカルPPA
フィジカルPPAは、PPA事業者が設置した太陽光発電設備でつくられた電気と、再生可能エネルギーの環境価値がセットで供給される方法です。
固定価格で取引されるので、市場価格の変動による想定外の支出を抑えられる点が特長です。一方で、太陽光発電設備でつくられた電気は送配電網を通して供給されるため、託送料金が発生します。自社の敷地内で発電するオンサイトPPAと比較すると、電気料金がやや高くなる可能性があるでしょう。
なお、2021年に電気事業法施行規則の一部が改正され、発電事業者と需要家で組合を設立するなどの経済産業省が定めた指針に従えば、PPA事業者を通さずに発電事業者と需要家が直接契約できるようになりました。直接契約した場合は、オフサイトPPAでも再エネ賦課金がかかりません。
バーチャルPPA
バーチャルPPAは、太陽光発電システムなどでつくられた再エネ由来の電力に含まれる環境価値のみを取引する方法です。電力の供給を伴わない点が、フィジカルPPAとは異なります。
バーチャルPPAでは、PPA事業者と需要家の間で再エネ由来の電力の価格・売買に関する契約を締結しますが、実際の電力供給は行いません。PPA事業者は、発電した電力を市場へ売電し、需要家は小売電気事業者から電力を購入します。契約時に取り決めた価格と市場価格に差がある場合は、その分をPPA事業者と需要家が相互に補填し、最終的に需要家へ環境価値の証書が渡る仕組みです。発電した電気は市場に売電されるものの、この差額精算によって取引全体で見るとコストを固定化できます。
具体的な支払い方法はPPA事業者によって異なるため、詳細は事業者にお問い合せください。
また既存の電力契約を維持したまま、実質的にCO2排出量を削減できる点も特長です。どうしても小売電気事業者を切り替えられないという企業でも、導入しやすいでしょう。
PPAモデルのメリット
PPAモデルを導入するメリットとして、主に以下の4つが挙げられます。
- 初期費用もメンテナンスも不要
- 電気料金を削減できる
- CO2排出量削減による企業価値向上
- BCP対策につながる
初期費用もメンテナンスも不要
PPAモデルでは、太陽光発電設備の購入や設置といった初期費用が不要なため、資金に余裕がなくても太陽光発電システムを導入できます。またメンテナンスや修理もPPA事業者にお任せできるため、自社での費用負担は必要ありません。
このように、太陽光発電システムの導入に必要なコストや手間を大幅に削減できる点が、PPAモデルの大きなメリットです。
電気料金を削減できる
PPAモデルを導入して消費電力の一部を自家消費に切り替えれば、電力会社から購入する電力量が減ります。PPA事業者に支払う電気料金は、従来の電気料金よりも安くなるケースが多いため、電力会社から購入する電力量が少なくなればなるほど電気料金を削減できるでしょう。
<電気料金の目安>
| 契約形態 | 1kWh当たりの電気料金・需要家のコスト | |
| 通常の電気料金(高圧) | 24.5円+再エネ賦課金 | |
| オンサイトPPA | 15~18円 | |
| オフサイトPPA | フィジカルPPA | 20~23円+再エネ賦課金 |
| バーチャルPPA | 37.5~40.5円-市場価格+再エネ賦課金 | |
※参考:自然エネルギー財団.「コーポレートPPA日本の最新動向 2024年版」.https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_JPCorporatePPA_2024.pdf ,(2024-09-28).
また電力会社から電気を購入する場合は、電力使用量に応じて再エネ賦課金がかかりますが、オンサイトPPAでははかかりません。
電気の消費量が多い企業がオンサイトPPAを導入すれば、消費電力の一部を自家消費に切り替えることができ、再エネ賦課金を含めて電気料金を削減できます。
さらにオンサイトPPA・オフサイトPPA共に、PPA事業者に支払う料金単価は基本的に固定となるため、市場価格の変動によって電気料金が上がるリスクを抑えられる点も特長です。
CO2排出量削減による企業価値向上
化石燃料を燃やさずに発電する太陽光発電は、発電時にCO2を排出しないため、環境への負担を減らすことが可能です。社会全体で地球温暖化対策への取り組みが重要視されている現在、CO2を排出しないクリーンな太陽光発電システムを導入しているとアピールすることで、企業価値の向上が期待できます。
昨今は「持続可能な開発目標」を意味するSDGsも注目されており、企業はSDGsの達成に向けた取り組みも社会的に要請されています。PPAモデルの導入によって再エネ由来の電気を使うことは、こうしたSDGsの要請にもマッチする取り組みです。
BCP対策につながる
太陽光発電システムは、蓄電池と併用することで非常用電源としても活用できます。
自然災害によって長時間の停電が発生するなど、企業活動に著しい損害がもたらされるような緊急事態に備え、事業継続のための手段などを取り決めた計画のことをBCP(事業継続計画)と呼びます。自家発電が可能な太陽光発電システムの導入は、このBCP対策として重要な取り組みであり、非常時に活用することで、企業の人的・経済的損失をできる限り小さくすることが可能です。なお、先述した通り、オフサイトPPAは、非常用電源としての活用はできません。
PPAモデルのデメリット・注意点
PPAモデルの導入にはデメリットや注意点もあります。主に以下の2点です。
- 長期契約が基本
- 太陽光発電システムの設置場所に制約がある
長期契約が基本
PPAモデルでは、10年以上にわたる長期契約を締結するのが一般的です。企業は通常、中長期的な事業計画を立てますが、社会・経済環境や市場の変化などによって計画通りに業績を維持・成長させることができず、例えば事業所の移転などを余儀なくされる可能性もゼロではありません。
自社の敷地内にある発電設備はPPA事業者が所有権を持つため、そうした場合でも勝手に撤去・廃棄することはできません。違約金が発生するケースもあるので注意が必要です。長期契約になることを踏まえ、事前に契約内容の確認を徹底しましょう。
太陽光発電システムの設置場所に制約がある
オンサイトPPAの場合、太陽光発電設備を設置する予定だった場所が発電に適していないなどの理由で、PPA事業者が需要家にメリットのある提案ができないと判断し、契約を締結できないことがあります。例えば日照時間が少ない、屋根の上の耐荷重が足りない、設置予定場所が十分な広さではない、積雪や塩害などへの対策を別途行わなければならないといったケースが典型例です。
PPAモデルの導入がおすすめな企業
以下のような企業は、PPAモデルの導入がおすすめです。
- 脱炭素化を目指している企業
- 長期的に電気料金を安定させたい企業
- 初期費用を抑えたい企業
- 保守管理の手間を減らしたい企業
脱炭素化を目指している企業
日本は2050年までにCO2をはじめとした温室効果ガスの排出量をゼロにする「カーボンニュートラル」を宣言しており、企業においても脱炭素経営を目指すことが求められています。
脱炭素化へ向けて何から着手すればよいか分からないという場合は、PPAの導入を検討してみてください。PPAを導入し、太陽光発電システムでつくられた電気を利用すれば、CO2排出量を削減できます。環境保全への取り組みは、企業のブランドイメージの向上や新規取引先の獲得にもつながるでしょう。
長期的に電気料金を安定させたい企業
日本は石油や天然ガスといった化石燃料の資源が乏しく、海外からの輸入に依存しています。国際情勢によっては化石燃料の需給がひっ迫し、電気料金が高騰するリスクがあります。実際に2022年のロシアによるウクライナ侵攻の開始以降、燃料価格は値上がりしており、ピークは過ぎましたが依然として高止まりしています。電気料金も2021年以前の水準に戻る気配はありません。
消費する電力量が多ければそれだけ大きな影響を受けるため、電気料金の高騰により利益が圧迫された、製品やサービスの値上げを余儀なくされたという企業も多いのではないでしょうか。
PPAモデルを導入すれば、先述した通り、PPA事業者に支払う料金単価は10年以上固定化されます。市場価格に左右されず、長期にわたって電気料金を安定させられるでしょう。
初期費用を抑えたい企業
PPAモデルでは、PPA事業者の所有する太陽光発電設備を初期投資不要で設置できます。
基本的にはPPA事業者が設備の設置費用などを負担するため、高額な初期費用を用意できない中小企業であっても比較的気軽に導入することが可能です。
保守管理の手間を減らしたい企業
太陽光発電設備を自社で保有している場合、定期的に保守管理を行わなければなりません。もちろんメンテナンスや修理にかかる費用も、自社で負担する必要があります。
PPAモデルであれば、契約期間中はPPA事業者が保守管理を行ってくれるため、企業の手間や時間、コストはかかりません。本来の事業活動に専念できるでしょう。
太陽光発電システムのPPAモデルを提供している主な事業者
太陽光発電システムのPPAモデルを提供している主な事業者を、一覧でご紹介します。PPAモデルの導入を検討している企業の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
| 事業者名 | 特徴 |
| 伊藤忠エネクス株式会社 | ・エネルギー総合商社として、60年以上の実績あり ・オンサイトPPA・オフサイトPPAの両方に対応 ・事前に企業の電力使用量や使用方法を分析し、適切なパネル容量を提案 |
| 丸紅新電力株式会社 | ・電力の取り扱い実績は20年以上 ・オフサイトPPAに対応 |
| NTTアノードエナジー株式会社 | ・オンサイトPPA・オフサイトPPAの両方に対応 ・セブン&アイグループや三井住友信託銀行などさまざまな企業での導入実績あり |
| 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | ・オンサイトPPAに対応 ・地方自治体・金融機関・地域企業とPPAに関する事業提携をし、脱炭素化を推進 |
| 関西電力株式会社 | ・オンサイトPPA・オフサイトPPAに対応 ・工事の時期を指定しない割引プランあり ・導入前の工事業者との調整から導入後の運用までサポートあり |
PPAモデルを導入する際に利用できる補助金
PPAモデルの導入促進のために、政府や地方自治体が補助金事業を行っています。ここでは、需要家がお得にPPAモデルを利用できる補助金を2つご紹介します。
なお、補助金の利用を検討する際には、Webサイトで公募状況や条件を細かく確認するようにしましょう。2024年10月時点で公募が終わっているものもあるので、翌年度も補助金の公募があるかどうかは公式サイトを確認してみてください。
【環境省】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業)」は、環境省が実施している補助金です。オンサイトPPAなどによる太陽光発電システムの導入や蓄電池の導入にかかる経費の一部に、補助金を利用できます。オンサイトPPAやリースの場合、サービス料金の低減などで、補助金額の一部が需要家に還元される点が特長です。ただし、太陽光発電設備(PPAモデル・自己所有型・リース)だけではなく、蓄電池の導入が必須となります。
| 対象者 | ・自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池などの導入を行う民間事業者 |
| 主な要件 | ・自家消費型の太陽光発電設備の導入を行う事業 ・導入する太陽光発電設備の「太陽電池出力」が10kW以上 ・定置用蓄電池もしくは車載型蓄電池の導入を行う事業 ・導入する太陽光発電設備による発電電力を導入場所の敷地内で自家消費する ・太陽光発電設備の発電した電力を余剰売電しない ・同一設備で、国からの別の補助金を併用しない |
| 補助額・補助率 | ・太陽光発電設備に対して、オンサイトPPAまたはリースの場合は5万円(/kW)、自己所有型の場合は4万円(/kW) |
| 詳細 | https://www.eic.or.jp/eic/topics/2024/st_r05c/002/ |
※参考:一般財団法人環境イノベーション情報機構. 「【三次公募のお知らせ】令和5年度(補正予算)および令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業の公募について」.https://www.eic.or.jp/eic/topics/2024/st_r05c/002/ , (2024-09-28).
【各地方自治体】省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金
「省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金」は、各地方自治体が実施している補助金です。オンサイトPPAやリースによって、自家消費型の太陽光発電設備を導入する際にかかる経費の一部を補助してもらえます。
先述した「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」と同様に、補助金相当額がサービス料金の低減などによって需要家に還元されます。要件や補助額などは地方自治体によって異なるので、詳細は各自治体のWebサイトを確認してください。一例として、滋賀県で実施されている補助金をご紹介します。
| 対象者 | 滋賀県内に事業所などを有する事業者 |
| 主な要件 | ・オンサイトPPAやリースによって自家消費型太陽光発電設備の導入を行う事業 ・需要家が中小企業など ・滋賀県で実施されるもの ・太陽光発電設備が自立運転機能を有している ・太陽光発電設備が発電出力5kW以上 ・蓄電池を導入する場合は、総蓄電容量3kWh以上かつ発電出力の同等以下であること |
| 補助額・補助率 | ・補助対象経費の3分の1以内もしくは需要家種別ごとに設定された上限もしくは発電出力1kW当たり7万円(オンサイトPPAの場合は4万円)のいずれか小さい額 ・災害時において地域の指定所に指定された施設については、補助対象経費の2分の1以内もしくは需要家種別ごとに設定された上限もしくは発電出力1kW当たり10万円のいずれか小さい額 |
| 詳細 | https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-240430-1129/ |
※参考:公益財団法人滋賀県産業支援プラザ. 「令和6年度 省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金」.https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-240430-1129/ , (2024-09-28).
まとめ
本記事では、太陽光発電システムの導入方法として注目を集めているPPAモデルについて解説しました。初期投資なしに太陽光発電システムを導入できるのみならず、メンテナンスの費用も不要で、電気料金の削減もできるなど、PPAモデルにはコスト面のメリットがたくさんあります。太陽光発電システムの導入にご興味をお持ちの方は、PPAモデルを検討してみてはいかがでしょうか。
伊藤忠エネクスでも自家消費型太陽光発電システム「TERASELソーラー」を提供しています。TERASELソーラーは、お客さまの保有施設に太陽光発電設備を設置し、発電した電気は自家消費可能です。当社へは定額もしくは従量払いにてサービス料(設備利用料やメンテナンス費用など)をお支払いいただきます。もちろん初期費用は不要です。太陽光発電システムの導入をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
「テラセルソーラー」のサービス詳細や導入事例は、以下のページをご覧ください。
03-4233-8055 平日 9:00~17:30キーワード検索
キーワード検索