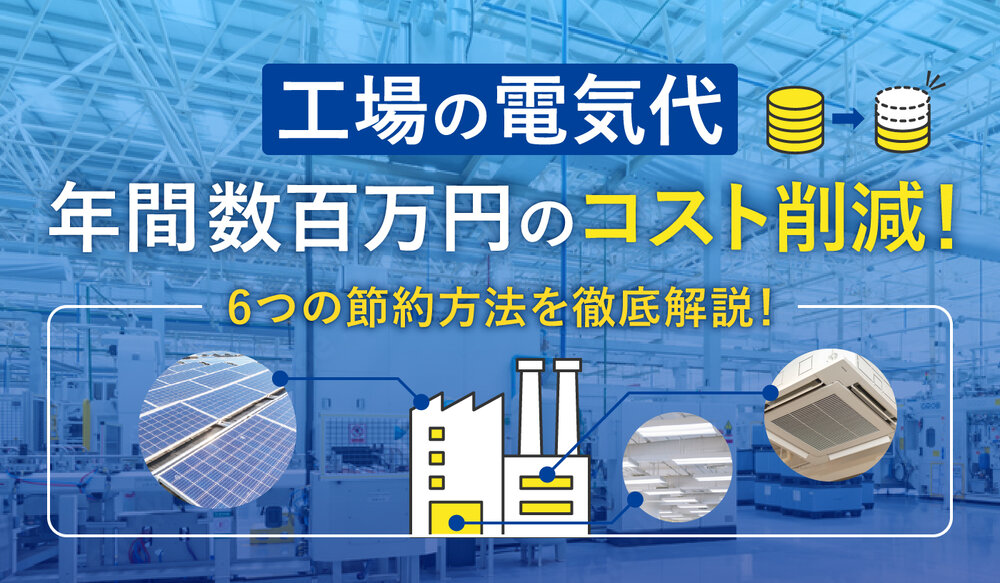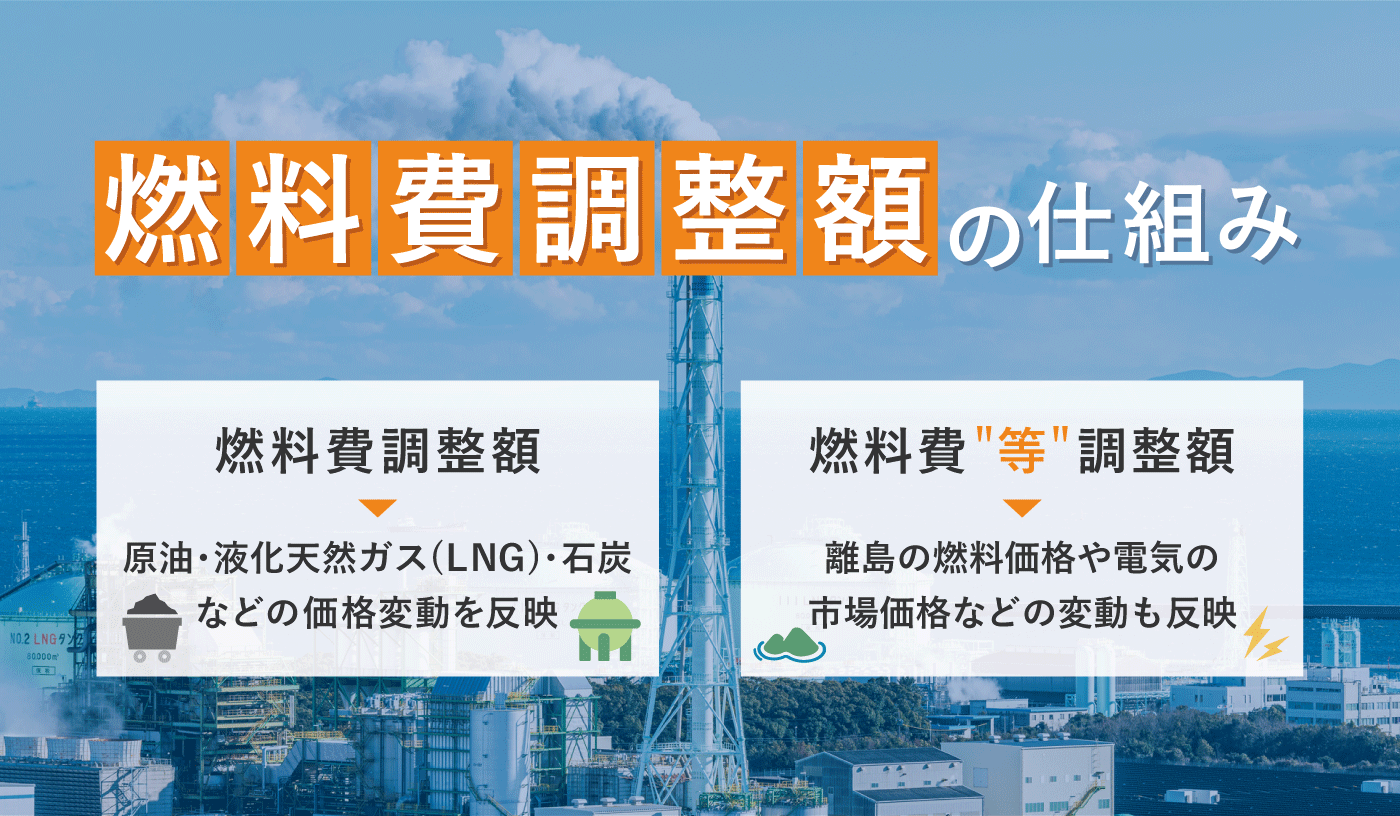Neste社に聞く、RD(リニューアブルディーゼル)の普及の鍵と今後の展望

2050年カーボンニュートラルへ向けて脱炭素化の取り組みが加速する中、日本においては軽油からRD(リニューアブルディーゼル)への燃料転換はまだ始まったばかりです。一方、欧米ではすでに建設や物流、データセンターといった多様な分野でRDの活用が進んでいます。
では、日本でRDを普及させるには何が必要なのでしょうか? 世界最大のRD製造元であるフィンランドのNeste社に、日本でRDを普及させるために必要なことや、将来の展望について伺いました。
※本記事は2025年1月時点の情報です
Neste社とは?
※出典:Neste.「About Neste」. https://www.neste.com/about-neste ,(2025-3-4).
Neste社はもともと石油精製会社でしたが、この10年間で、再生可能エネルギーおよび循環型ソリューションの世界的リーダーへと変革を遂げました。Neste社はRD(リニューアブルディーゼル)およびSAF(Sustainable Aviation Fuel)の世界最大の製造元であり、ポリマーや化学製品の再生可能・循環型原材料の開発においても業界をリードしています。
「私たちNesteのすべての取り組みは「子どもたちのために、より健康な地球を創る」という目的のもとに行われています。この目的に突き動かされ、大気中に放出される炭素の量を削減する新しい方法を模索し、炭素を何度も再利用できる循環型ソリューションを開発することに取り組んでいます。」(Neste社の担当者)
Neste社が開発した独自のNEXBTL™技術により、さまざまな種類の廃棄する油や残留油(例:廃食油、廃動物油脂など)を高品質な再生可能製品へと変換できるようになりました。Neste社がこのNEXBTL™技術の特許を取得してからすでに25年以上が経過しており、フィンランド・ポルヴォーのNeste製油所で最初のNEXBTL™ユニットが稼働してからは15年が経過しています。
長年にわたり技術革新と持続可能なエネルギーへの転換に取り組んできたからこそ、Neste社は再生可能エネルギーおよび循環型ソリューションの世界的リーダーになることができたのです。
世界で普及するNeste社のRD(リニューアブルディーゼル)
※出典:Neste.「Renewable diesel」. https://www.neste.com/products-and-innovation/neste-my-renewable-diesel ,(2025-3-4).
Neste社のRD(リニューアブルディーゼル)は、ブランド名として「Neste MY Renewable Diesel™」と呼ばれています。軽油の代替燃料で、世界各国で導入が進んでいます。以下に各国におけるNeste MY Renewable Diesel™の導入事例をまとめました。
※Neste MY Renewable Diesel™とRenewable Dieselでは、性状などは全く変わりません
| 業界 | 国名 | 企業名 | 主な取り組み | 成果 |
| 建設 | オーストラリア | Marr Contracting | オーストラリアでの重機用ルフィングタワークレーンの運用にNeste MY Renewable Diesel™を使用 詳細はこちら | ・温室効果ガス(GHG)排出量の削減 ・軽油や従来型バイオ燃料と比較して、エンジンオイルやエンジン、燃料フィルターがクリーンな状態を維持できている |
| 採掘 | アメリカ | Rio Tinto | アメリカの事業所で採掘用ダンプトラックの燃料をRDに切り替えることを目指している。NesteおよびRolls-Royceとの提携のもと、2022年に初めてRDの試験運用を実施 詳細はこちら | 2024年までにすべての重機をRDへ完全移行することで、年間最大45,000トンのCO2e排出削減見込み |
| 海運 | シンガポール | KPI OceanConnectおよびGlobal Energy | シンガポールの海運業界にNeste Renewable Dieselを供給 詳細はこちら | ・海運業界における持続可能な燃料の使用促進が期待される ・環境負荷の軽減が期待される |
| 物流 | オーストラリア | Cleanaway Waste Managemen | 試験運用において、オーストラリア国内の2台のトラックにNeste MY Renewable Diesel™を導入 詳細はこちら | 軽油と比較して温室効果ガス(GHG)排出量を最大91%削減 |
| 物流 | ドイツ | BMW | 2022年12月より、ドイツ・ミュンヘンのBMW工場と物流拠点を結ぶトラックがNeste MY Renewable Diesel™を使用。2023年3月には、DB Schenkerの6台のトラックにも拡大 詳細はこちら | 年間最大800トンのCO2e排出削減が期待される |
| 交通 | ドイツ | Deutsche Bahn | 2023年にNeste MY Renewable Diesel™を約13,300トン(1,700万リットル)を購入し、ディーゼル機関車や鉄道車両に使用 詳細はこちら | 約46,000トンのCO2e排出削減を実現 |
| 航空 | ドイツ | Hamburg Airport | すべてのディーゼル駆動の地上車両をNeste MY Renewable Diesel™で運用するドイツ唯一の空港 詳細はこちら | – |
| データセンター | シンガポール | ST Telemedia Global Data Centres | バックアップ発電機用燃料としてNesteのHVO(加水分解植物油)を導入 詳細はこちら | 最初の供給量は50,000リットルで、温室効果ガス(GHG)排出量を最大90%削減 |
| データセンター | ベルギー | LCL | 2022年12月より、Neste MY Renewable Diesel™を緊急用発電機に使用するパイロットプロジェクトを開始 詳細はこちら | – |
| データセンター | フィンランド | Verne | フィンランドのヘルシンキ、ポリ、タンペレのデータセンターでNeste MY Renewable Diesel™を使用 詳細はこちら | – |
| メーカー | イギリス | Rolls-Royce | MTUエンジンにNeste Renewable Dieselの100%使用を承認 詳細はこちら | – |
| メーカー | ドイツ | MAN Engines | 欧州のEN15940規格およびアメリカのASTM D975規格に準拠するRDを、すべてのディーゼル船舶エンジンで使用可能とする決定を発表 詳細はこちら | – |
日本でRD(リニューアブルディーゼル)が普及に至るまでの課題
日本では、伊藤忠商事がNeste社のRD(リニューアブルディーゼル)を輸入・調達し、伊藤忠エネクスが供給・販売しています。例えば、ファミリーマートの配送車両や西武バスの旅客バス、全日本空輸株式会社の羽田空港の地上支援機材(GSE)などでNeste社のRDが使われていますが、日本での認知度はまだまだ低いのが現状です。日本でRDが普及に至るまでの課題はどこにあるのでしょうか?
Neste社の担当者は「日本において道路輸送でのRDの利用をさらに促進するためには、特定の政策による支援が必要です」と述べています。
日本でRD(リニューアブルディーゼル)を普及させる鍵は政策の支援
世界各国では、国や自治体が政策によってRD(リニューアブルディーゼル)の普及を支援しています。以下に各国における政策事例をまとめました。
| 国名(自治体名) | 政策内容 |
| オーストラリア | 現在、燃料品質基準法(Fuel Quality Standards Act)の改訂が進行中で、2025年にRDの供給を可能にするためのパラフィン系ディーゼルの規格が導入される可能性がある |
| 韓国 | 道路輸送向けの混合目標として2030年までに8%(HVO 3%、バイオディーゼル 5%)の導入を計画 |
| スウェーデン | バイオ燃料の目標割合を引き下げていたが、バイオ燃料の義務付けが再導入された |
| フィンランド(ポルヴォー市) | ポルヴォー市がフィンランドで初めて、すべてのディーゼル車両にNeste MY Renewable Diesel™を導入 |
RD(リニューアブルディーゼル)の価格は本当に課題?
第2世代以降のバイオ燃料の課題の一つとして製造コストの高さが挙げられます。軽油や従来型バイオ燃料と比較するとどうしても燃料単価が高くなってしまうため、RD(リニューアブルディーゼル)の導入に対して二の足を踏んでいる企業もあるでしょう。ですが、本当にRDの価格は高いのでしょうか?
Neste社の担当者は「化石燃料のコストには、温室効果ガス(GHG)の排出や気候への影響にかかる本当のコストが含まれていません。従って、本当に問うべきなのは「RDを使用しなかった場合のコストはどのくらいか?」という点です」と述べています。
単に燃料単価を比較するのではなく、RDと軽油、従来型バイオ燃料(FAME)が持つ価値を理解し、それぞれの温室効果ガス(GHG)排出削減率を考慮する必要があるということです。加えてRDには、軽油や従来型バイオ燃料(FAME)と比較して燃焼時に煤が出にくい、匂いが低減されるといったメリットも挙げられます。
また「より適切に比較するなら、脱炭素化の選択肢としてRDと電動化の「総所有コスト(TCO:Total Cost of Ownership)」を比較するのがよいでしょう」ともNeste社の担当者は述べています。
TCOとは製品やサービスを導入・運用するために発生する総コストのことで、導入費用だけではなく、利用や運用にかかる維持費用やエネルギーコスト、修理・メンテナンスの費用なども含まれています。例えば、車両の脱炭素化を進める場合、RDであれば車両はそのままで燃料だけを切り替えればよいですが、電気自動車であれば車両を入れ替えたり、車両を充電するための設備を導入したりする必要があります。一方で、エネルギーコストを比較すると、RDを購入するよりも、電気自動車の充電にかかる電気料金の方が安いかもしれません。燃料単価だけではなく、総合的なコスト評価が重要なのです。
Neste社の今後の展望
※出典:Neste.「Sustainability Report 2023」. https://www.neste.com/sustainability/reporting ,(2024-3-1).
ここまで、世界のRD(リニューアブルディーゼル)の導入事例や、日本での普及に必要なことを伺ってきましたが、最後に世界最大のRD製造元であるNeste社の将来の展望についてお聞きしました。
「Nesteは2030年までに顧客の温室効果ガス(GHG)排出量を少なくとも年間2,000万トン削減することを目指しています。またフィンランド・ポルヴォーのNeste製油所をヨーロッパで最も持続可能な製油所にすることを目指しており、2035年までにカーボンニュートラルな生産を達成することにコミットしています。この変革は、NesteのScope1-3の温室効果ガス(GHG)排出量削減を大幅に後押しすることになります。
今後Nesteにとって最も重要なのは、Scope3の当社が生産・販売する製品の使用段階での温室効果ガス(GHG)排出量です。Nesteは2040年までに販売製品の炭素排出強度を50%削減することを目標に掲げています。この目標を達成するために、製品ポートフォリオにおける再生可能エネルギーおよび循環型ソリューションの割合をさらに増加させていきます。
またその他のScope3領域として、購入した原材料やサービス、輸送および物流に関連する温室効果ガス(GHG)排出量が、Nesteのサプライチェーン排出量の削減にとって重要なテーマとなります。当社は組織全体での能力強化を継続し、サプライヤーやパートナーと協力してScope3のアクションプランを策定していきます。」(Neste社の担当者)
さらに、Neste社は生物多様性、人権、サプライチェーン管理においても高い基準を設定しており、世界で最も持続可能な企業のリスト(CDPおよびDJSI)に継続的に選出されています。以下にNesteのサステナビリティ・ビジョン(日本語訳)を掲載しますので、ぜひ脱炭素化に向けた目標を策定する際の参考にしてみてください。
| 分野 | 目標 |
| 気候(Climate) 2040年までにカーボンニュートラルなバリューチェーンを実現 | ・2030年までに顧客の温室効果ガス(GHG)排出量を年間少なくとも2,000万トン削減 ・2019年比で2030年までに自社の生産時排出(Scope1&2)を50%削減し、2035年までにカーボンニュートラル生産を達成 ・2040年までに販売製品の使用段階での排出強度を2020年比で50%削減 ・サプライヤーやパートナーと協力し、バリューチェーン全体の排出(Scope3)を削減 |
| 生物多様性(Biodiversity) 2040年までに生物多様性へのプラスの影響を促進し、「ネイチャーポジティブ」なバリューチェーンを実現 | ・2025年以降、新規事業による生物多様性への影響をネットプラス(NPI)にすることを目指す ・2035年までに既存事業における生物多様性のネットロスゼロ(NNL)を達成 |
| 人権(Human Rights) 2030年までに、すべての人が尊厳を持って働ける、公平で包摂的なバリューチェーンの実現を目指す | ・2030年までにすべての従業員に生活賃金(リビングウェージ)を支払い、サプライチェーンにおいても生活賃金の支払いを促進 ・2030年までに高リスク地域で雇用者負担の原則(Employer Pays Principle)を導入し、労働者が雇用のための費用を支払うことがないようにする ・2030年までに教育へのアクセス向上を促進し、子どもの権利を支援 ・2030年までにバリューチェーン全体の格差を減少させ、人権問題の根本的な原因に取り組む |
| サプライチェーンと原材料(Supply Chain & Raw Materials) 安全で健康的な職場環境、公正な労働慣行を推進し、サプライチェーン全体で持続可能性の向上を促進 | ・100%のサプライヤーおよびビジネスパートナーが「Nesteサプライヤー行動規範」に署名し、最高水準の苦情処理プロセスを導入 ・持続可能な原材料の調達を拡大するため、サプライヤーに対して人権、生物多様性、気候目標を主要評価基準として設定 |
まとめ
日本が脱炭素社会を実現するためには、Scope2に該当する電気の転換以外にも、Scope1とScope3に該当する化石燃料からバイオ燃料への転換も不可欠です。先述した通り、RD(リニューアブルディーゼル)は燃料を軽油から切り替えるだけで、既存の車両や設備を交換・新設することなく利用できるため、比較的手軽に取り入れられる脱炭素化ソリューションとして注目されています。世界の事例のように、数台の車両から試験導入することも可能です。ぜひ、Neste社と伊藤忠エネクスとともに、RDの普及に取り組んでみませんか?
伊藤忠エネクスでは全国の輸送用トラックやバス、建設機械、船などの燃料としてNeste社のRDの提供を行っています。伊藤忠エネクスはISCC(国際持続可能性カーボン認証)を取得しており、また2024年6月21日にはRDが合成燃料の類型として初のエコマーク商品に認定されました。さらに、輸入・調達元の伊藤忠商事および供給・販売元の伊藤忠エネクスはRDの全国展開を目指し、軽油に最大40%のRDを混和した「RD40」の製造・供給を進めています。100%RDは軽油と混ぜることはできませんが、RD40は地方税法上の軽油に該当するため軽油との併用が可能です。走行中に燃料が不足した際に軽油を継ぎ足せるので、より利便性が向上するでしょう。
脱炭素経営を目指している企業や軽油からの燃料転換に興味がある企業は、お気軽に伊藤忠エネクスにお問い合わせください。RDに関する疑問点や使用場所、対象をお伺いいたします。
リニューアブルディーゼル
03-4233-8073 enex_hvo@itcenex.comキーワード検索
キーワード検索