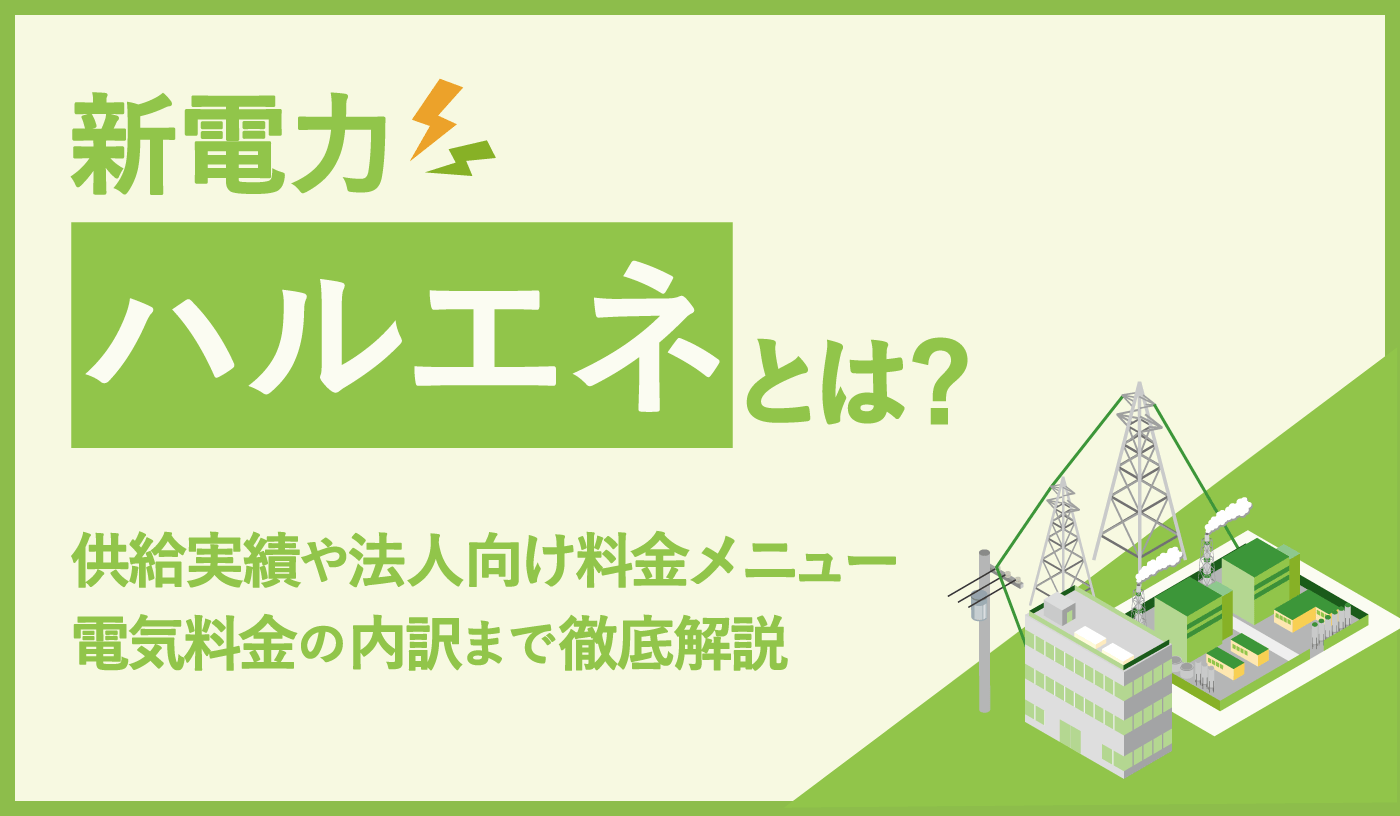太陽光パネルは減価償却で節税できる? 法定耐用年数の考え方や会計処理の方法を解説

資産の増加や老後に備える方法として個人投資が増えている中、安定的な収入が見込めて節税効果もあると注目を集めているのが太陽光発電投資です。太陽光パネルやパワーコンディショナー、土地などを購入する初期費用はかかるものの、設備は減価償却できるので投資した分を経費として計上しながら、早めに投資回収を済ませることも可能です。
しかし、減価償却は計算式に用いる法定耐用年数が用途によって異なったり、償却の方法が複数あったりするので、やや分かりにくい印象をお持ちの方もいるでしょう。そこで本記事では、太陽光パネルをはじめとする発電設備を減価償却する際の法定耐用年数の考え方や、会計処理の方法を解説します。
※本記事の内容は2025年3月時点の情報です
※本記事でご紹介している税金の具体的な計算については、皆さまの個々のご事情によって異なりますので、大変お手数ですが、最寄りの税務署または税理士などにご相談いただきますようお願いいたします
目次
太陽光パネルは減価償却費の経費算入が可能
太陽光発電システムが減価償却の対象になるかどうかは、事業の用に供しているか否かで判断されます。減価償却の対象となる場合、個人なら「所得税」の申告時に、法人なら「法人税」の申告時に減価償却費を経費算入できます。法人であれば事業の用に供していることが明らかですが、個人の場合は判断が難しいこともあるでしょう。ここでは、個人が所有する太陽光発電システムが減価償却の対象になる例を解説します。
継続的に売電収入を得ている場合や住宅兼事務所に太陽光パネルを設置する場合は、事業の用に供するケースに該当します。国税庁では、住宅兼事務所に設置した太陽光パネルで余剰売電したケースについて「事業所得の付随収入」になると明記しています。たとえ事務所が住宅と兼用であるとしても、太陽光パネルで作った電気が事務所の業務に利用されている限り太陽光パネルは事業用資産(=減価償却資産)と見なされるからです。ただしこの場合、減価償却費の全てを経費算入できるわけではなく、発電した電気のうち事務所に使用した割合と売電した割合を合計して事業用割合とし、その割合に応じた部分のみ経費算入できると考えられます。
※参考:国税庁.「自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」. https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/45.htm ,(2025-03-12).
減価償却とは?
そもそも減価償却とは、資産のうち時間の経過とともに価値が減っていくものを毎年分割して経費計上することです。事業の用に供しており、取得金額が10万円以上かつ1年以上使用するものであれば、個人も法人も減価償却費を経費算入できます。ただし、資産の中には減価償却費を経費算入できる資産とできない資産があるので、注意が必要です。
| 区分 | 特徴 | 主な例 | |
| 減価償却費を経費算入できる資産 | 有形減価償却資産 | 長期的に収益を生み出すことが可能で、形のある資産のこと | 太陽光発電システム建物車両製造・農業に使用する機械 など |
| 無形減価償却資産 | 長期的に収益を生み出すことが可能で、形のない資産のこと | 漁業権商標権ソフトウェア など | |
| 生物 | 長期的に収益を生み出すことが可能な動植物。成熟したタイミングから減価償却が可能 | 乳牛や繁殖用の豚りんご樹 など | |
| 減価償却できない資産 | 非減価償却資産 | 長期的に利用が可能で、形のある資産のうち価値が減少しないもののこと | 土地の権利骨董品 など |
減価償却費を経費算入できる資産は長期的に収益を生み出すため、取得費と利益を正確に対応させる必要があります。そのため購入した年度に一括で経費計上するのではなく、減価償却費として資産の価値や耐用年数に合わせて毎年経費を計上します。
太陽光パネルの法定耐用年数
法定耐用年数とは、法律で定められた固定資産の使用可能年数のことです。各メーカーが定める「通常の使用方法で、問題なく利用できる年数(耐久年数・耐用年数)」もありますが、課税所得を計算するための減価償却では法定耐用年数を用いるので注意しましょう。
太陽光パネルは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」内にある「機械及び装置の耐用年数表」の「31 電気業用設備のうち主として金属製のもの」に該当するので、法定耐用年数は17年です。
※参考:e-GOV.「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」.https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/ , (2025-01-25).
電気の使用用途によって法定耐用年数が異なる場合がある
法人の場合、太陽光発電システムで作った電気を使用して、他の製品(最終製品)を生産することがあります。その場合、太陽光発電システムがその最終製品に関する設備と見なされて、法定耐用年数が17年ではなくなることがあるため、注意が必要です。国税庁が太陽光発電システムに17年以外の法定耐用年数を適用した事例を詳しく見てみましょう。
| 太陽光発電システムの所有者 | 自動車製造業を営む法人 |
| 対象となる設備 | 自社の工場構内に設置した太陽光発電システム |
| 設置の目的 | 自動車製造設備を稼働させるための電力を発電する |
| 国税庁の見解 | 太陽光発電システムで作った電気によって自動車が生産される場合、当該の最終製品は自動車であり、自動車製造の設備として判定をする。したがって「輸送用機械器具製造業用設備」に該当し、法定耐用年数は9年となる。 |
ただし「必ずしも事案の内容の全部を表現したものではない」と明記されている通り、業種によってはこの事例が当てはまらないケースもあります。現在所有しているあるいはこれから購入しようとしている太陽光パネルの法定耐用年数が何年になるのかは、税務署に問い合わせてみましょう。
※参考:国税庁.「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」.https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm ,(2025-01-25).
※参考:e-GOV.「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」.https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/ , (2025-01-25).
減価償却を会計処理する2つの方法
減価償却の方法には、大きく分けて定額法と定率法の2つがあります。納税者が会計処理の方法を決定し、納税地を管轄する税務署長に届け出を行います。届け出をしない場合は、以下のルールで計算しましょう。
- 個人(所得税):原則、定額法
- 法人(法人税):原則、定率法(ただし、建物や構築物、ソフトウェアなどは定額法)
ここでは2つの計算方法の概要やそれぞれが適しているケースについて解説します。
定額法
定額法とは、毎年同じ額の減価償却費を計上する方法です。定額法の減価償却費は以下の計算式で求めます。
| 減価償却費 = 資産の取得価額 × 定額法の償却率 |
定額法の償却率は法定耐用年数ごとに異なり、法定耐用年数が17年の太陽光パネルを2007年4月1日以降に取得した場合の償却率は0.059です。償却率は国税庁の「減価償却資産の償却率等表」を参照してください。
100kWの太陽光パネルを設置した場合を例に、定額法の減価償却費を算出してみましょう。なお、取得価額は購入対価 + 付随費用で算出します。本記事では、経済産業省が公表する太陽光パネルの取得費用(50~250kWの区分) = 1kW当たり6.8万円 × 100kW = 680万円を取得価額と仮定して減価償却費を算出します。
- 減価償却費 = 680万円 × 0.059 = 40万1,200円
定額法の場合、法定耐用年数の期間中、残存簿価が1円になるまで毎年同額の減価償却費を計上します。この例では、初年度から16年目までは40万1,200円、17年目のみ未償却の資産額から1円を差し引いた額を計上します。ただし、年度の途中で太陽光パネルを取得した場合、初年度は月割り額を計上するので注意しましょう。
※参考:経済産業省資源エネルギー庁.「太陽光発電について」.https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/091_01_00.pdf ,(2025-01-25).
定額法での処理が適しているケース
定額法は毎年同額を計上するため、安定した課税所得を維持したい個人や法人に適しています。詳しくは後述しますが、定率法と比べると購入した当初の減価償却費が少ないため、初年度に利益を多く残したい場合も定額法を選びましょう。
法人の場合、定額法を利用するためには届け出が必要になります。
定率法
定率法とは、未償却の資産額に償却率を乗じた減価償却費を計上する方法です。定率法の減価償却費は以下の計算式で求めます。
| 減価償却費 = 未償却の資産額(資産の取得価額 – 前年までに減価償却した累計額) × 定率法の償却率 |
定率法の償却率も法定耐用年数ごとに異なり、法定耐用年数が17年の太陽光パネルを2012年4月1日以降に取得した場合の償却率は0.118です。ただし、減価償却費が償却保証額を下回ったら、それ以降は残存簿価が1円になるまで償却保証額を毎年経費として計上します。
| 償却保証額 = 資産の取得価額× 保証率 |
法定耐用年数が17年の保証率は0.04038です。保証率も国税庁の「減価償却資産の償却率等表」を参照してください。
100kWの太陽光パネルを設置した場合を例に、定率法の減価償却費を算出してみましょう。先述した通り、取得価額は購入対価 + 付随費用で算出します。本記事では経済産業省が公表する太陽光パネルの取得費用(50~250kWの区分) = 1kW当たり6.8万円 × 100kW = 680万円を取得価額と仮定して減価償却費を算出します。
- 減価償却費(初年度) = 680万円 × 0.118 = 80万2,400円
- 減価償却費(翌年度) = (680万円 – 80万2,400円) × 0.118 = 70万7,716円
- 減価償却費(3年目) = (599万7,600円 – 70万7,716円) × 0.118 = 62万4,206円
- 償却保証額 = 680万円 × 0.04038 = 27万4,584円
このように定率法の場合は、初年度の減価償却費が一番多く、年を経るごとに減少します。この例では、初年度から9年目まではこの計算方法で減価償却費を算出し、10年目から16年目までは償却保証額の27万4,584円を計上、17年目のみ未償却の資産額から1円を差し引いた額を計上します。
※参考:経済産業省資源エネルギー庁.「太陽光発電について」.https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/091_01_00.pdf ,(2025-01-25).
定率法での処理が適しているケース
定率法は、一定期間までは減価償却できる費用が定額法よりも多いです。そのため、初期の税額を抑えたい場合は定率法が適しています。個人事業主の場合、定率法を利用するためには届け出が必要になります。
太陽光パネルを減価償却するメリット
太陽光パネルを減価償却するとどのようなメリットを得られるのでしょうか。ここでは個人・法人を問わずメリットになる点をご紹介します。
節税になる
減価償却の最大のメリットは、節税になることです。先述した通り、土地は減価償却費を経費算入できない資産なので、必要経費として計上することができません。その点、太陽光パネルは減価償却費を経費算入できるので、比較すると節税効果が大きいです。例えば、1,900万円で購入した資産で90万円の収益が出ている場合、差し引く経費が無ければ90万円に対して税金を納める必要があります。
しかし、毎年20万円分の減価償却費を算入すれば、課税対象となる収益は70万円に減ります。納める税金が少なくなればより多くの利益を手元に残すことができるでしょう。
損益を適切に把握できる
太陽光パネルの取得費用を減価償却すれば、投資額が初年度のみに経費計上されず、使用する期間にわたり案分されるので損益を正しく把握できます。減価償却では、定額法・定率法のいずれかの方法でその年に計上する経費を算出します。売電による収益に対してどのくらいの経費がかかったかが分かれば、投資に対する利益率を把握しやすくなります。また毎年どのくらいの経費がかかるかをあらかじめ把握することもできるので、長期的な事業計画を考えやすくなるでしょう。
太陽光パネルを減価償却する際の注意点
減価償却はメリットが多い反面、理解しておくべきルールもいくつかあります。正しく減価償却を行う上で注意すべきポイントをご紹介します。
法定耐用年数をしっかり確認する
先述した通り、減価償却の計算をする上で、法定耐用年数は重要な要素です。法定耐用年数を間違えてしまうと算出される減価償却額が変わってしまうので、修正の申告が必要となる場合があります。太陽光パネルの場合、法定耐用年数を17年とする場合とそれ以外の年数を適用する場合があるので、取得した設備は何年になるのかを会計処理をする前に必ず確認しておきましょう。
償却方法は3年間変更できない
先述した通り、個人(所得税)は原則定額法、法人(法人税)は原則定率法により減価償却費を経費算入します。資産の性質によっては選べないものもありますが、個人が定率法を、法人が定額法を選択することも可能です。ただし、どちらの方法を選択しても特別な理由がある場合を除き、3年間は変更することができません。初年度の償却額が多い定率法を選び、翌年度からは定額法に切り替えるといったことはできないので注意しましょう。3年後に償却方法を変更する場合は、所轄の税務署で変更手続きを行ってください。
設備を処分した際に除去処理を忘れない
個人も法人も、太陽光パネルを処分した場合は除却処理を行い、対象の資産を会計帳簿から除却する必要があります。この会計処理を行わないと翌年度以降も減価償却が続いてしまい、保有していない資産に対しての償却資産税が課税される可能性があるため、注意しましょう。
太陽光パネルは何年発電ができる?
太陽光パネルの法定耐用年数は17年です。しかし、これはあくまでも会計処理上の年数であり、実際に稼働可能な年数(耐用年数)は20〜30年といわれています。つまり太陽光パネル自体は17年を過ぎてもしばらく使い続けることが可能です。
太陽光パネルの耐用年数が長いと、2つの点で保有者にメリットがあります。1つ目は、太陽光パネルが故障するまで安定した売電収入を維持できる点です。これまでの実績からどのくらいの収益が得られるかの予測も立てやすいので、節税効果が薄れても保有を続ける方が多いです。
2つ目は、セカンダリー(中古)市場への売却も可能である点です。太陽光パネルは耐用年数が長いので、減価償却が終了しても設備としては使い続けられます。そのため買い手が付きやすく、現金化しやすいです。
投資を目的に太陽光発電システムを所有しているなら、市場の需要が高いうちに売却することで投資効果をさらに高められるでしょう。
まとめ
事業の用に供している太陽光パネルは減価償却できるため、節税をしつつ利益を多く残すことができます。損益を適切に把握できれば、長期的なキャッシュフローの計画も立てやすいです。減価償却の会計処理は2種類あり、個人であれば原則定額法、法人であれば原則定率法を採用します。
また太陽光パネルは稼働可能な耐用年数も20~30年と長いので、減価償却期間を過ぎても安定した収益を維持できます。納税負担が気になる場合は、需要の高いセカンダリー市場への売却も選択肢の一つです。
すでに太陽光発電システムを保有しており売却について検討しているなら、伊藤忠エネクスの太陽光発電所買い取りサービスがおすすめです。エネルギー商社として60年以上にわたって培ってきた知識やノウハウを生かし、お持ちの太陽光発電所を適正価格で買い取ります。メーカーの保証期間が過ぎているものや、海外メーカーの太陽光パネルでも買い取りが可能です。投資の出口戦略として太陽光発電所の売却を検討しているなら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※本記事でご紹介している税金の具体的な計算については、皆さまの個々のご事情によって異なりますので、大変お手数ですが、最寄りの税務署または税理士などにご相談いただきますようお願いいたします
太陽光発電所買い取りサービス
03-4233-8073 enex_hvo@itcenex.com一緒に見られている記事
RECOMMEND
キーワード検索
キーワード検索