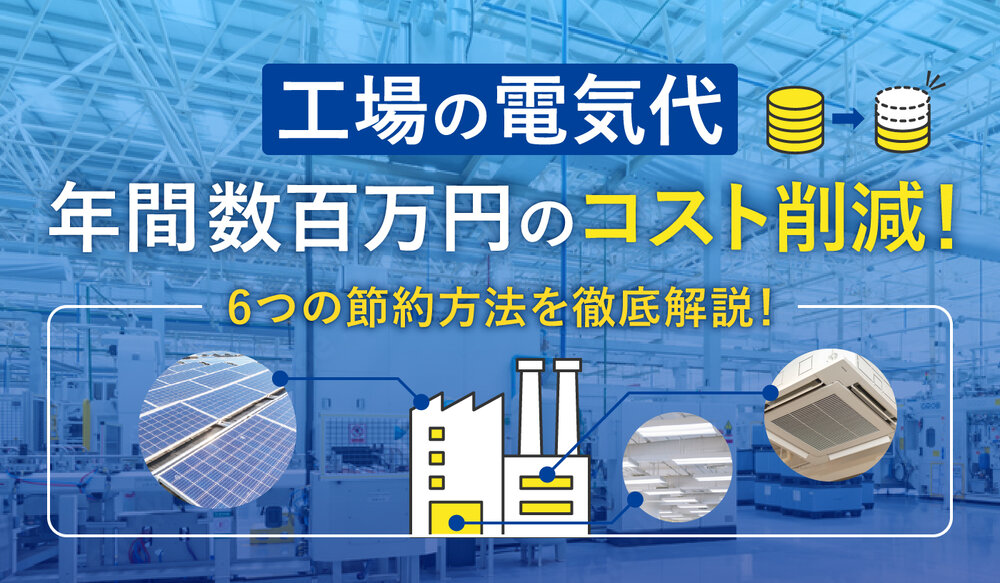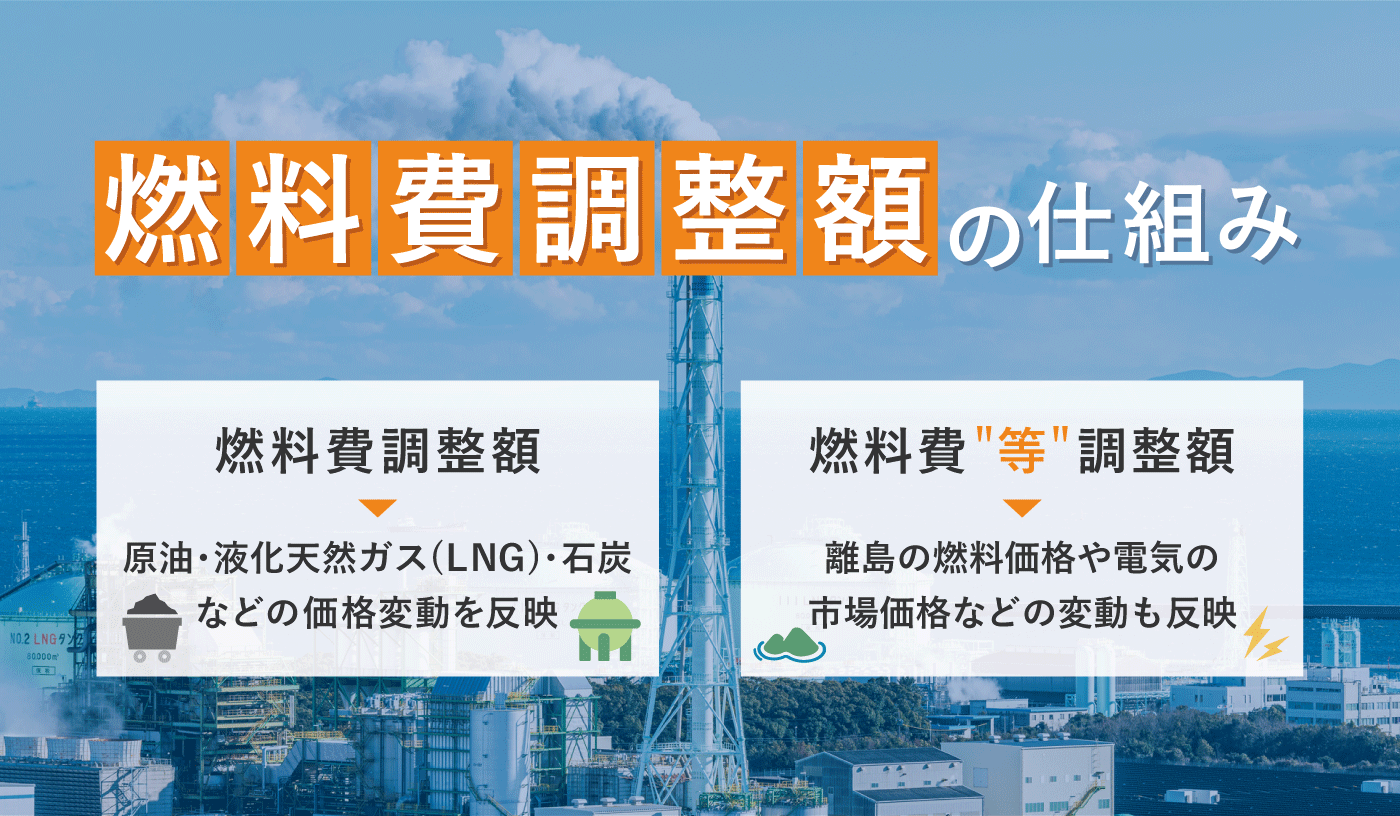太陽光発電システムを所有すると固定資産税がかかる? 対象となる設備や計算方法を徹底解説
太陽光発電システムの所有・売却時にかかる税金とは? 具体的な節税対策を解説

太陽光発電システムの運用をしていると、さまざまなタイミングで異なる税金を納める必要があります。個人事業主や個人投資家の方はご自身で税務処理を行わなければならないため、どのような税金があるのか、どのような対策を行う必要があるのかをしっかりと理解しておくことが重要です。
本記事では、太陽光発電システムの所有時と売却時にかかる税金と節税対策の方法について、詳しく解説します。法人成りしている方向けに法人税についても併せて解説するので、ぜひ参考にしてください。
※本記事の内容は2025年3月時点の情報です
※本記事でご紹介している税金の具体的な計算については、皆さまの個々のご事情によって異なりますので、大変お手数ですが、最寄りの税務署または税理士などにご相談いただきますようお願いいたします
目次
太陽光発電システムの所有時にかかる税金とは?
ここでは、太陽光発電システムを所有しているときにかかる税金について解説します。税金の種類によっては課税対象にならないケースもあるので、詳細を確認しておきましょう。
償却資産税
償却資産税とは固定資産税の一部で、毎年1月1日時点で事業に使用する目的で所有している機械や備品に対してかかる税金です。資産が所在する市町村(東京都23区の場合は東京都)へ、申告内容に基づいた税金を納付します。
太陽光発電システムは固定資産のうち、時間の経過とともに劣化して価値が減っていく償却資産に当てはまるため、償却資産税がかかります。しかし、中には償却資産税がかからないケースもあるので、ご自身が所有する太陽光発電システムがどちらに該当するのかを確認しておきましょう。
償却資産税がかからないケース
償却資産税がかからない可能性がある太陽光発電システムの要件は、以下の通りです。
- 作った電気の使用目的が「生活利用」
- 発電出力容量が10kW未満
- 太陽光パネルが屋根の上に置かれた架台に設置されている
- 太陽光発電システムの課税標準合計額が150万円以下
作った電気を生活のために利用する場合は「事業利用されない資産」と見なされるので、償却資産税がかかりません。ただし、太陽光パネルが屋根と一体になっている場合は家屋の性能を高める設備としてみなされて固定資産税の対象となり、家屋の評価額が上がる可能性があります。自治体によっても判断が分かれるので、詳しくは償却資産が所在する市町村(東京23区の場合は東京都)へ問い合わせてください。また住宅でカフェを経営していたり事務所として利用していたりすると、作った電気の全てが生活利用ではないと判断され、償却資産税の対象になる場合があります。
発電出力容量が10kW未満の場合、住宅用区分に該当するため償却資産に当たらないと判断される可能性があります。また太陽光パネルが架台に設置されている場合も、家屋とは別の資産と見なされるので償却資産税の対象外となる可能性があります。ただし、事業の用に供している場合は、どちらも償却資産税の対象となるので注意しましょう。
個人の需要家の場合、課税標準合計額が150万円以下の場合も償却資産税は免除されます。課税標準合計額とは、取得価額(購入した価格と付随する価格の合計額)と耐用年数を基礎として評価した額の合計のことです。ただし、課税標準合計額は他の償却資産と合わせて150万円を下回る必要があるので、注意してください。
太陽光発電システムにかかる償却資産税については以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
所得税
所得税とは、個人の1年間の所得金額から所得控除を差し引いた課税所得金額にかかる税金です。所得には給与所得や不動産所得、事業所得といった10種類があり、それぞれ必要経費の範囲や計算方法が異なります。太陽光発電の売電収入がどの所得に分類されるかはケースバイケースです。
例えば、住宅用太陽光発電システムを生活利用で導入しており余剰電力を売電した場合は、利益は雑所得に分類されます。一方で、事業として継続的に売電収入がある場合は事業所得に分類されます。
所得税は累進課税を採用しているため、所得金額が多いほど税率が高くなり、多くの税金が課されます。
所得税がかからないケース
雑所得の合計が20万円を下回る場合、確定申告が不要です。そのため余剰電力を売電していても年間の利益が20万円を超えなければ、所得税を納める必要がないのです。
ただし、2カ所以上から給与を受け取っている場合や、給与所得と退職所得を除いた各種所得の合計金額が20万円を超える場合は、確定申告が必要となるので注意しましょう。必然的に雑所得も申告の対象となります。
住民税
住民税とは、個人の前年の所得金額から所得控除を差し引いた課税所得金額にかかる税金です。前年の所得に対して10%の税率をかける「所得割」と、所得の金額に関係なく定額で負担する「均等割」の2つを合算して算出します。
住民税は所得額や扶養親族の有無、また未成年者、障がい者、ひとり親、寡婦のいずれかであるといった条件に当てはまる場合、非課税になるケースがあります。住民税の非課税条件に当てはまらない方は、所得税上は確定申告が不要の場合でも、住民税の申告は行う必要があります。
個人事業税
個人事業税とは、個人事業主の所得が290万円を超えた場合にかかる税金です。地方税法で定められた70業種に該当する場合、税金を納める必要があります。
太陽光発電事業は、法定業種の第1種事業のうち電気供給業に当たり、税率は5%です。
個人事業税がかからないケース
個人事業税は、年間の事業所得・不動産所得の金額の合計が290万円を下回ると非課税となります。事業を始めて1年未満の場合は、事業開始から経過した月数に応じて設定された控除額以下であれば、税金を納める必要がありません。
また個人事業主が青色申告で赤字を3年間繰り越し、その結果所得が290万円以下になった場合も課税対象外となります。
法人税
法人税とは、法人が事業活動などで得た所得に対してかかる税金です。個人であっても法人成りしている場合は、所得税ではなく法人税を納めます。法人税率は、資本金が1億円以下の企業とそれ以外の企業で、以下のように変わります。
| 区分 | 法人税率 | ||
| 資本金1億円以下の法人 | 年間所得800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
| 適用除外事業者 | 19% | ||
| 年間所得800万円以上の部分 | – | 23.2% | |
| 上記以外の法人 | 23.2% | ||
適用除外事業者とは、その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人などをいいます。
例えば、資本金1億円以下の法人かつ適用除外事業者に該当しない、年間所得が1,000万円の場合は、以下の計算式で法人税を算出します。
- 所得800万円までの部分の税額 = 800万円 × 15% = 120万円
- 残りの所得200万円分の税額 = 200万円 × 23.2% = 46万4,000円
- 税額の合計 = 120万円 + 46万4,000円 = 166万4,000円
株式会社や合同会社、有限会社といった営利目的の法人は全て課税対象となります。
※参考:国税庁. 「No.5759 法人税の税率」.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm ,(2025-01-29).
地方法人税
地方法人税とは平成26年の税制改正によって施行された税制度です。その名称から地方自治体に納める税金に思われがちですが、国税の一つです。地方法人税は、地域間での税収のバラつきをなくすことで地域格差を縮小することを目的としています。
地方法人税は、基本法人税額の10.3%です。先述した資本金1億円以下の法人かつ適用除外事業者に該当しない、年間所得が1,000万円の場合の地方法人税は、以下の計算式で算出します。
- 地方法人税額 = 166万4,000円 × 10.3% = 17万1,300円(100円未満切り捨て)
法人事業税
法人事業税とは、法人が行う事業そのものに対してかかる税金です。課税対象は法人税と同じく所得で、翌年度に費用として税金を計上できるのが特徴です。また法人税は国に納める税金ですが、法人事業税は地方自治体に納める税金という違いがあります。
法人事業税は、所得に法人事業税率をかけて算出します。税率は都道府県によって異なるので、各都道府県へご確認ください。
法人住民税
法人住民税は、法人の所得に対してかかる税金「法人税割」と法人の規模に応じてかかる税金「均等割」を足したものです。
法人税割は、国に納めた法人税額に税率をかけて算出します。均等割は資本金等の額ならびに従業員数によって、9つの区分で定められた額を納めます。
法人税と法人事業税は所得を基に算出するので、赤字の年度は納税額が0円となりますが、法人住民税のうち均等割は、赤字年度でも納税する必要があるので注意しましょう。
太陽光発電システム所有後に行える節税対策
太陽光発電システム所有時にかかる税金のうち、売電収入にかかるさまざまな税金の負担をなるべく抑える方法を解説します。
設置にかかった費用を減価償却する
太陽光発電システムは減価償却資産に該当するため、設備の取得費用は減価償却することが可能です。減価償却とは、太陽光発電システムの取得費用を毎年分割して経費として計上することです。太陽光発電システムの場合、売電収入から経費を差し引いた金額が所得として課税の対象となるので、減価償却によって課税対象額を減らすことができ、節税になります。
課税所得を計算するための減価償却では法定耐用年数を使用し、太陽光発電システムの法定耐用年数は17年です。ただし法人の場合、作った電気の使用目的や業種によっては、法定耐用年数が変わるケースもあるので、判断に迷ったら税務署へ問い合わせてください。
※参考:e-GOV.「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」.https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015/ , (2025-01-25).
※参考:国税庁.「風力・太陽光発電システムの耐用年数について」.https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm ,(2025-01-25).
運用にかかる費用を経費として計上する
経費として計上できるのは、太陽光発電システムの取得費用だけではありません。例えば、太陽光発電システムにかけている火災保険や動産総合保険、賠償責任保険などの保険料も経費として計上できます。
また安定した発電を維持するために欠かせないメンテナンスや定期点検費用も、経費の対象です。2017年に改正されたFIT法では設備のメンテナンスが義務化され、発電出力容量が50kW未満の場合は4年に1回程度、50kW以上の場合は太陽光パネルやパワーコンディショナーといった設備は6カ月に1回程度、受変電設備は2~6カ月に1回程度点検を行う必要があります。実施したら漏れなく経費に計上しましょう。
他にも、太陽光発電システム取得のために組んだローンの利息や設置場所の地代も経費として計上が可能です。
※参考:一般社団法人太陽光発電協会.「メンテナンスや点検はどうすればいいですか?」.https://www.jpea.gr.jp/faq/579/ ,(2025-01-29).
太陽光発電システムを売却する際にかかる税金とは?
2023年度に東京電力の管轄エリアを除く全てのエリアで、一時的に発電量を抑える出力制御の要請が出たこともあり、今後の売電収入の減少リスクを懸念して、太陽光発電システムの売却を検討している方もいらっしゃるでしょう。そこでここからは、太陽光発電システムを売却する際にかかる税金について解説します。
譲渡所得税
個人が太陽光発電システムを売却すると、譲渡所得に対して税金がかかります。譲渡所得は、以下の計算式で算出できます。
- 譲渡所得 = 売却額 – (太陽光発電システムの購入金額 – 売却時までに減価償却した合計額)- 譲渡費用(手数料など) – 特別控除(50万円)
譲渡所得がプラスになったら、確定申告をする必要があります。太陽光発電システムは総合課税の対象です。対象となる所得を合算した上で合計額に対応する税率を確認しましょう。なお、総合課税には累進課税制度が適用されます。
設備と合わせて土地も売却する場合、土地は分離課税の対象になります。土地の譲渡に対する税金は、以下の計算式で算出できます。
- 譲渡所得税 = 譲渡所得 × 所得税率
土地は所有期間によって税率が変わります。詳しくは後述します。
住民税
太陽光発電システムを売却した際の所得には、住民税も課されます。個人の前年の課税所得金額にかかる点や税率は、所有時にかかる住民税と同じです。
なお、設備と合わせて土地も売却する場合、その所得にかかる税率は所有期間によって変わります。詳しくは後述します。
消費税
太陽光発電システムを生活利用してきた個人が太陽光発電システムを売却した場合、消費税はかかりません。個人事業主が売却した場合、消費税の扱いは以下の2点によって変わります。
- 事業用の資産か生活用の資産か
- 課税事業者か免税事業者か
太陽光発電システムが事業用の資産の場合、課税事業者には消費税が課されます。課税事業者とは消費税の納税義務がある事業者のことで、基準期間において消費税がかかる売上高が1,000万円を超える事業者などを指します。
一方、課税事業者の個人事業主が生活用の資産を売却した場合や、個人事業主が免税事業者の場合は消費税が課されません。免税事業者とは、その名の通り消費税の納税義務を免除されている事業者のことです。基準期間での課税売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者となります。ただし、基準期間後に課税売上が1,000万円を超えたら課税事業者となり、消費税を納めなければなりません。
また法人が太陽光発電システムを売却した場合は、課税事業者か免税事業者かで消費税の扱いが変わります。
なお、売却額に上乗せする消費税は、売却価格に10%を乗じて計算します。
法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税
法人が太陽光発電システムを売却したときの所得には法人税や地方法人税、法人事業税、法人住民税がかかります。課税対象や税率は、売電収入時と同じ扱いです。
太陽光発電システムの売却時に行える節税対策
ここでは、太陽光発電システムを売却する際に実践したい節税対策をご紹介します。売却するタイミングにもかかわるので、当面売却の予定が無くても把握しておきましょう。
導入から5年以内の売却は避ける
先述した通り、太陽光発電システムの売却による譲渡所得は総合課税の対象です。総合課税の譲渡所得は、資産の所有期間によって課税対象が変わります。
| 総合課税の譲渡所得の区分 | 課税対象 |
| 所有から5年以内(短期譲渡所得) | 譲渡所得金額の全額 |
| 所有から5年超(長期譲渡所得) | 譲渡所得金額の2分の1 |
所有から5年が経過すると、課税対象が譲渡所得金額の2分の1になるため、太陽光発電システムは導入から5年が経過してから売却をする方が、納税金額を抑えられるのです。
一方、太陽光発電システムを設置している土地は、分離課税の対象です。分離課税の課税所得は、資産の所有期間によって税率が変わります。
| 分離課税の譲渡所得の区分 | 所得税 | 住民税 |
| 所有から5年以内(短期譲渡所得) | 30% | 9% |
| 所有から5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% |
所有期間が5年経つ前に売却してしまうと納税負担が重くなってしまうので、なるべく避けましょう。
※参考:国税庁.「No3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm ,(2025-01-30).
※参考:国税庁.「土地や建物を売ったとき」.https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm ,(2025-01-30).
消費税を軽減する
先述した通り、免税事業者であれば消費税を納める必要がありません。例えば税込1,100万円で太陽光発電システムを売却した場合、消費税額である100万円を納税しなくてもよいので、その分売却益を確保できます。
なお、基準期間の売上高に関係なく課税事業者を選択していた事業者が免税事業者になるには、税務署に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。ただし、基準期間において課税売上高が1,000万円を超える事業者は免税事業者になれないので、注意してください。
課税事業者のまま消費税を軽減するなら、簡易課税制度を利用すると有利になる可能性があります。簡易課税制度とは、基準期間において課税売上高が5,000万円以下の中小事業者が適用できる課税方式です。
一般的には、原則課税制度を用いて消費税を算出します。
- 納税額 = 売上にかかる消費税額 – 仕入れにかかる消費税額
一方で簡易課税制度は、仕入れにかかる消費税額の代わりに業種ごとに定められた「みなし仕入れ率」を売上にかかる消費税額に乗じて納税額を算出します。計算式は以下の通りです。
- 納税額 = 売上にかかる消費税額 – (売上にかかる消費税額 × みなし仕入れ率)
みなし仕入れ率を定める事業区分は第1~第6まであり、太陽光発電システムは第3種事業に該当します(みなし仕入れ率は70%)。仕入れにかかる消費税率が少ない場合、簡易課税制度を適用した方が納付額を少なくできるので、節税効果が期待できます。しかし、全ての事業者に当てはまるわけではないので、簡易課税制度を適用する前に原則課税制度と納付額を比較して、どちらが適しているのかを確認しましょう。
一旦簡易課税制度に変更すると2年間は元に戻せないので、中期的な視点で比較検討することが大切です。
※参考:国税庁.「No.6505 簡易課税制度」.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm ,(2025-01-30).
まとめ
太陽光発電システムにまつわる税金には、資産そのものにかかる税金や売電収入にかかる税金、売却時にかかる税金などがあり、他の所得がある場合は複雑な税務処理を行う必要があります。本記事を参考にいつ・どのような税金がかかるのかを把握し、申告漏れが起こらないようにしましょう。
特に太陽光発電システムを売却する際は、所有期間によってかかる税率や課税対象が変わるので、市場価値を把握しながらベストなタイミングを見極めることが重要です。お持ちの太陽光発電システムの売却価格を知りたい方は、伊藤忠エネクスの太陽光発電所買い取りサービスをご活用ください。
伊藤忠エネクスはエネルギー商社として60年以上の歴史があり、これまで蓄積してきた知識やノウハウ、自社で太陽光発電所を運営している経験を生かして、太陽光発電所を適正価格で買い取ります。
売電収入が減ってきている、修理やメンテナンスの手間がかかる、そろそろFIT期間が終了するといったお悩みがある方は、ぜひお気軽に伊藤忠エネクスへご相談ください。
※本記事でご紹介している税金の具体的な計算については、皆さまの個々のご事情によって異なりますので、大変お手数ですが、最寄りの税務署または税理士などにご相談いただきますようお願いいたします
太陽光発電所買い取りサービス
03-4233-8073 enex_hvo@itcenex.comキーワード検索
キーワード検索